賢くなりたいひとは多い。そのために、本を読むことを選ぶひともいる。
最近は、Web コンテンツが増え、賢くなるために本を読むという人はすくなくなってきたように思うが、やはり一番の近道は本を読むことだと思う。
本は「知見を広め、世界を広くする」ものだと信じている。
しかし、なかには「本を読んでも意味がない」と言うひとがいる。それを、かつて熱心に本を読んでいたひとが言うこともある。意味のない読み方(間違ったやりかた)をしていたのか?と疑いたくなる。
たとえば、すでに知っていることを読む場合、世界は広がらない。これは「賢くなる」という目的がある人からすれば、「データをあつめるだけの意味のない読み方」になるだろう。
(「本を読んだ」という満足感はあるかもしれないが。)
賢くなるためには───世界を広くするためには、未知を読む必要がある。
けれど、じっさいに本を読むときはそんなことまで考えないだろう。興味のあるものを読むし、表紙のインスピレーションに頼るひともいるかもしれない。
それで本選びを間違えるひとがいる。そういう経験を何度もしていると、「本は読んでも意味がない」などとトンチンカンなことを言いだすのかもしれない。
目次
本選びは難しい
では、じっさい賢くなるためにはどんな本を読めばいいのだろうか。
軽く触れたが、"未知" を読めばいい。
テーマはなんでもよいが、歴史・文化あたりは無駄にならないことが多い。べつに茶道などでもかまわない。いままで触れてこなかったものを手に取り、パラパラと読むだけでいい。かならず世界が広がる。
ただ、未知を読むといっても、どんな本にすればいいか分からないひとが多いことを知っている。文庫本にすればいいのか、重版にすればいいのか、入門書がいいのか、こども向けのものがいいのか、迷うことを知っている。
(現代には本が増えすぎた。)
せっかく読むのであれば、テーマは選びたい、できれば自分の興味のあるものを選びたい、役に立ちそうなものを選びたい。そういう気持ちもわかる。そういうことを考えていると、どんな本を読めばいいのか分からなくなる。
第一段階で、いろいろ面倒になる。このカベに阻まれた者は本を手にすることもできない。その日のうちに、本を探していたことも忘れてしまう。
第二段階で、ネットでおススメされている有名な本をさがしてくる。書店でそれを見つけ、手に取ってみる。「まずはカンタンなものから」という想いが首をもたげたら、その隣の入門書っぽい本を手に取る。
第三段階で、読もう読もうと思っているが、腰が重たくなる。モチベーションが少しずつなくなって、読むのが面倒になってくる。「本当に賢くなれるかわからない」と思ってしまったらもう駄目である。本を棚にしまい、そのうえにはマンガが平積みされる。
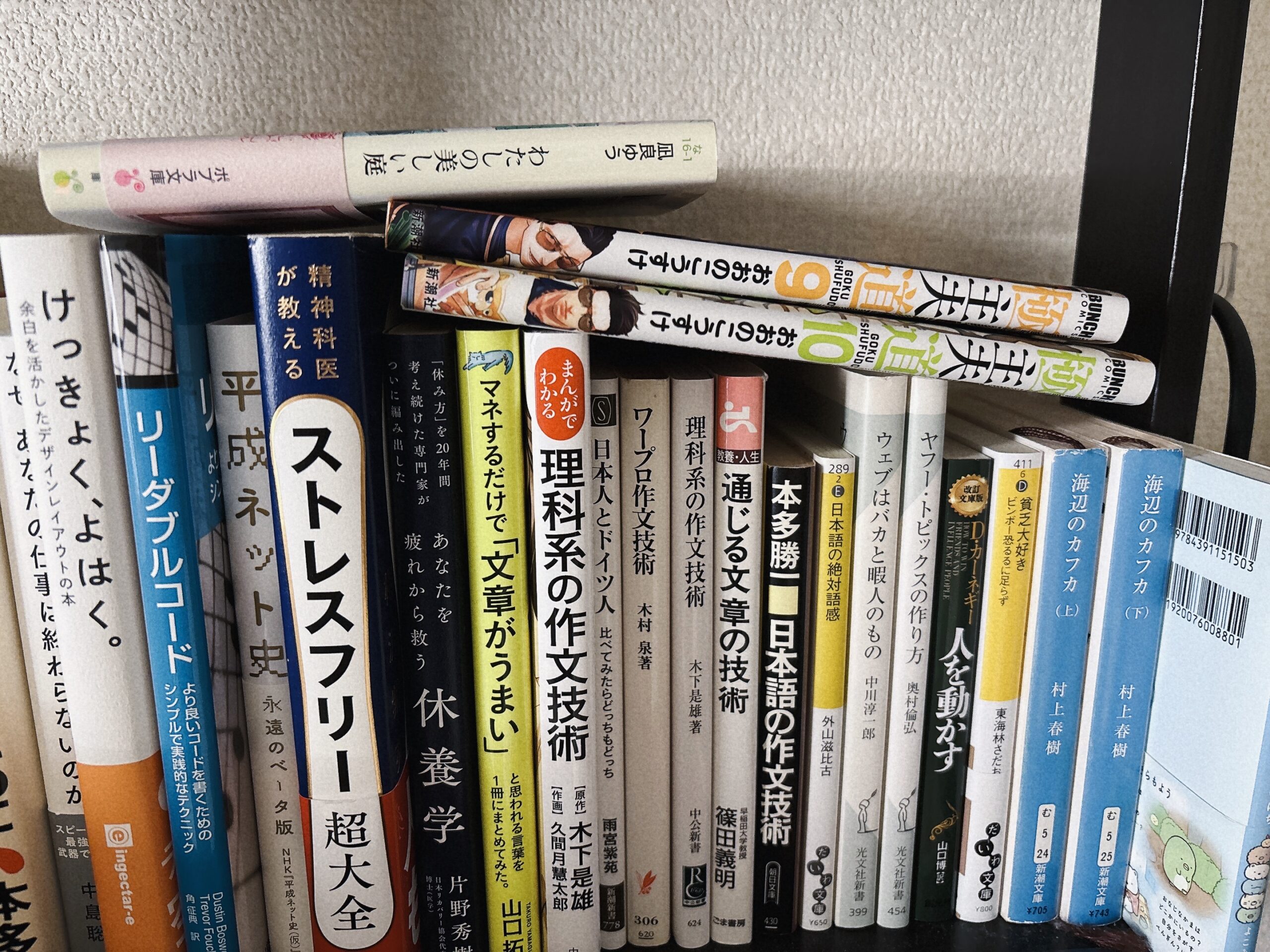
これは「意思」や「やる気」に関係なくおこる。「面倒くさい」という感情は、人間の行動をおそろしくコントロールするからだ。
さらに厄介なものがある。「読んでも賢くなれるかわからないよなぁ」という想いである。この想いはその本に対してよほどの信頼がないかぎりはつきまとう。そして面倒くさいと非常に仲がいい。
1冊読むのには時間がかかる。未知を読むのであればなおさらだ。失敗はしたくない。とりあえず読んでみる前に、もっといい本がないのかを探したくなる。
そうなると最初から信頼できる本を手にしたい。───しかし、それは難しい。それで、なかなかに読書はこれうまく進まない。
「賢くなるため」というボヤッとした目的であればなおさらだ。
岩波新書はスゲェって話
けれど、じつは「賢くなりたい」という目的があるのであれば、これを知っているだけで、本選びは迷わない。
つまりは、黙って岩波新書(岩波文庫)を読めばよろしい。
賢くなりたいなら、まずは古典を読むべき。これは一般化してもいいと思う。そして、岩波新書は古典を多く出している。「出版社の特徴」として、硬派な本しか出さないのだ。だから、岩波新書を読めば、10年も20年も役にたつ知識を手に入れることができる。
その普遍性(=一般性)はすごい。
聞いた話によると、本を書きたいという人がどんなに有名であっても、その業界で一般的とされている論でないと書かせてもらえないのだとか、そのまま大学の教養課程で使用されるような知識レベルでないとダメだか、いう。
ことばを選ばずにいえば───
- 採算がとれるはずもないクソ難解な古典的名著を、無謀にも出している。
- 原典尊重主義である。原則省略をせず、退屈な部分も愚直に収載する。
- 外国の古典で、原語がかなりレアであっても、極力原語から訳している。
- 日本の古典は、原則校異のみで注釈は載せない。
こういうことをしているので、全世界の歴史的な名著が、わずか数百円で読める。
また、そのジャンルは多岐にわたる。読む本は自分の好きなジャンルでもよいし、そうでなくてもよい。そのときに興味のあるテーマを選んで読むことができる。
岩波新書を愛読しているというひとは、本物の知識人だと思う。
本は、くりかえし読める本を選びたい
とにかく、本は絶対に選んだ方がいい。そして、迷ったら岩波新書(岩波文庫)を手に取ればよい。さらに言えば、くりかえしくりかえし読める本を選びたい。
岩波新書は難しいので、1回で理解しようとしなくていい。
一度読み、二度読み、それでも足りないので三度読む。それでも分からない。分からないけど、いつか分かるときが来るのだろうかと想いを馳せる。
そうやって温めていると、いつか本当にわかるときがくる。いままでツンとしていたのに、ひょっこり顔を出したと思ったら、フレンドリーに話しかけてくる。昔の人は、それを「読書百遍意おのずから通ず」ということばで表現した。
--
最近、Books&Apps でこんな記事を読んだ。
橘玲さんの亜玖夢博士の経済入門 (文春文庫) という本の中で、「ねえ知ってる?ひとは自分が見たいものを、見るんだよ」というセリフが出るシーンがある。
僕はこのセリフの意味が、最初に読んだ時は全然よくわからなかった。その当時の僕は、どちらかというと嫌な現実ばかりが目の前にあるように感じられる日々が続いており
「全然みたいものなんて見れないじゃないか」
と、強く憤りを感じていたからである。
しかし、それから随分と月日が流れ、改めてこのセリフを読み直すと、確かに人は自分がみたいものしか見ていないな、と思う。
出典:Books&Apps.「本を読み返すと、人生は少し生きやすくなる」(2025/5/13) - https://blog.tinect.jp/?p=89569
「人生は、何度か見返すと景色が変わる」ということが書かれた記事だ。記事の最後が「だから良い本は良い本であるほどに、再読する必要があるものなのだ。」と締められており、感銘をうけた。
記事では小説が例として取り上げられていたが、これは「賢くなるための本」も言えるのではないかと思った。
未知を読むのは相当に疲れる。
けれど、そうやって手に入れた「賢さ」は生涯いきる。
かんばっていきましょう。
以上です。