note で、「#わたしの旅行記」というお題の執筆イベントがあった。
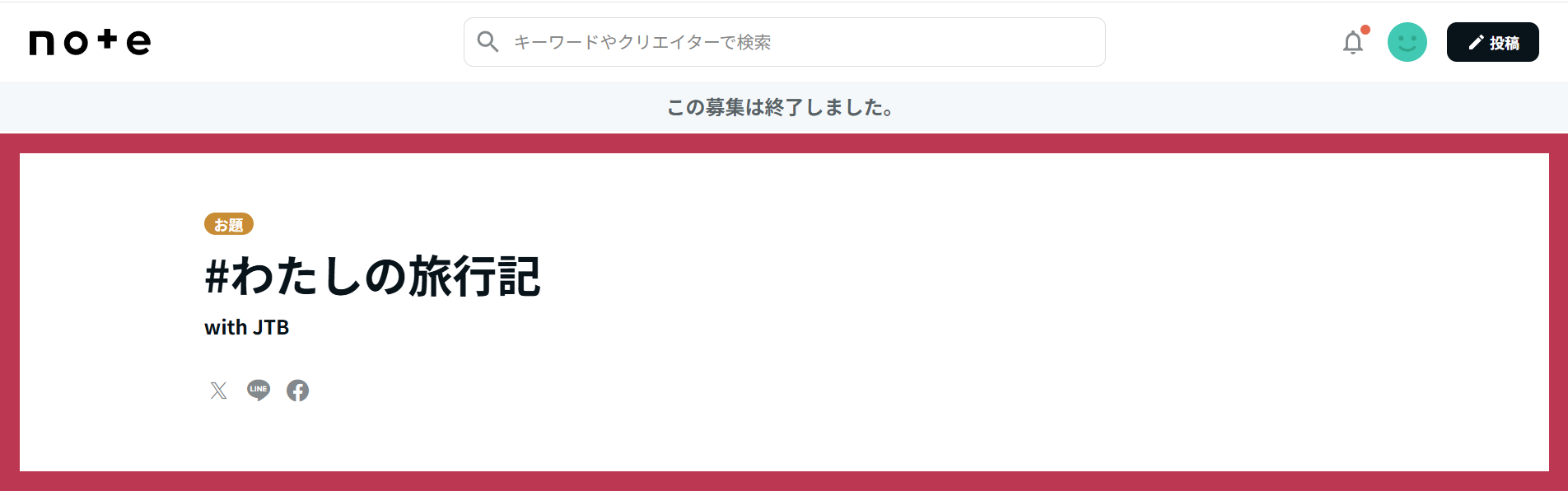
旅行には縁がない私だが、読み物は大好きだ。タイトルがおもしろそうなものをいくつか読んでみた。そのなかに、いくつか「なんだこれ」とネガティブな意味で気になるものがあった。
「なんだこれ」の正体、それは「お前、いつになったら目的地に着くねん!」である。
旅行の経緯を書くだけで100文字。
準備について語っていたら、あっという間に300文字。
ようやく出発したと思ったら、新幹線までの道のりだけで300文字。
駅で駅弁を迷っていて100文字。
車窓からの景色を書き連ねていたら、また500文字。
隣に座っていた子どもがお菓子をこぼした、それだけの話に100文字。
───けっきょく、私は彼女が目的地に着く前に読むのをやめてしまった。
note なので、書き手はプロではない。ただの日記であると割り切ればいい。けれど、別に読むことを強要されているわけでもない。読むのが辛いと、すぐに閉じればいい。
--
そういう文章を読んで、以前、ルポタージュは「いきなり現場型で書け」といった主張が書かれた本を思い出した。
少し長くなるが、引用する。
文章の冒頭、書き出しの方法についてもまた落語には学ぶべきところが多い。どの落語家も「エエ毎度バカバカシイ……」といった挨拶をほんの一言か二言話すだけで、いきなり「オーイ熊さんや」などと本筋にはいる。これだ。読み手を早く自分のペースに引きずりこむには、序論みたいなものをクドクド書いていてはだめだ。論文であればなるべく早く問題の核心へ、紀行文であればなるべく早く現地へはいる方がよい。
(…)
紀行文を検討してみよう。第四章で引用した『モゴール族探検記』(梅棹忠夫)の冒頭は、いきなり国境から始まっている。それまでの、日本を出発してからパキスタンとアフガニスタンの国境へ着くまでにあったであろうたくさんのことは、いっさい省いてしまった。読者はいきなり国境───しかも日本との国境ではなく、遠い中東の国境に立たされる。
本田 勝一『日本語の作文技術』P246 朝日文庫(1982年)
私が求めていた旅行記はこれだった。
当時はルポタージュなんて「戦場カメラマンかよ」と思っただけで、あまり深く読んでいなかった。私はルポライターではないし、旅行ライターになる予定もなかった。関係がないと思っていた。
けれど、いまや雑記を書くようになり、「もしかしたら旅行記くらい書くかもな」と思った。そういうワケで、あらためて本を引っぱりだしてきて、読み返してみた。
目次
いきなり現場型とは
書きだしは記事にとって非常に重要な要素だ。これは「旅行記」に限らず、記事全般に一般化してしまってよいだろう。多くの文章読本でも冒頭の重要性は語られており、いまさらどこからか引用しようとも思わない。
私も、記事を書くときには内容よりも、書き出しをどうするべきか考える時間の方が多いことも珍しくない。よい冒頭ができれば、それをベースに記事がすすむ、なんてこともある。
───で、そんな冒頭の代表的な手口のひとつに「いきなり現場型」というものがあるらしい。序論的なものは一切なく、事件そのものにいきなりはいる方法である。読者をひきつけるための定石のひとつだという。
現場でなくても、アップから始めるテクニックもある。
たとえば、漁師を写すのに手先のアップから始める。読んでいるひとは手元であることしか最初はわからない。いったい何だ、と思う。この「何だろう?」と一瞬好奇心を起こすことを狙っている。何のことかわからないから、わかろうとして熱心になる、その連続で読者を引きずりこんでいく。
--
現代において、前置きが長いのは「悪」でもある。
いまの人は多忙である。まどろっこしい前置きを、ぐだぐだのべていれば、かんしゃくをおこして、さきの話など聞いてくれない。文章なら投げ出してしまう。単刀直入に行くべきである。
外山 滋比古『知的文章術』P146 大和書房(2024年)
書き手としては、準備や移動、道中の景色など、書きたいことはたくさんあるだろう。そうした要素も旅の醍醐味には違いない。ただ、それをダラダラと書き連ねると、読者はへきえきしてしまう。
いきなり現場型の良例
「いきなり現場型」の説明はサラッと流した。ダラダラ説明をくべるよりも、じっさいの文を見せた方が早いと思ったからだ。
3つの文を紹介したい。これらはすべて川端康成の本の冒頭だ。旅行記にも同じことがいえるかわからないが、こんな冒頭が書けたなら、よろこんでトランクに荷物をつめる描写など消してやろうと思う。
国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた。夜の底が白くなつた。信号所に汽車が止まつた。
───『雪国』
「雪国」の世界を正面にすえて、象徴的に幕を開く。きっぱり言い切るのがいい。
鎌倉円覚寺の境内をはいつてからも、菊治は茶会へ行かうか行くまいかと迷つていた。
───『千羽鶴』
「境内へはいつてからも」の「も」という助詞があるため、その前から迷っていたことを意味する。読者にとっては、物語がいつのまにかはじまっていたことになる。
私は二十歳、高等学校の帽子をかぶり、紺飛白(こんがすり)の着物に袴をはき、学生カバンを肩にかけていた。一人伊豆の旅にでてから四日目のことだった。修善寺温泉に一夜泊り、湯ヶ島温泉に二夜泊り、そして朴歯の高下駄で天城を登ってきたのだ。
───『伊豆の踊り子』
”私”の説明についても着目したい。帽子から始まって、上から下へと順序よく進めている。最初に旅情と若さ、そして孤独をうまく表現している。
メルヴィルの『白鯨』などは、冒頭で鯨に関する文献が延々と並ぶ。前半に鯨学や捕鯨学がいっぱい出てくる。非常に難解だ。それでも多くの読者は、これがアメリカ文学の古典だと宣伝されているので、我慢して読む。また、「わかりにくいことは高級なのだ」という迷信にとりつかれる。
しかし、私が彼女の旅行記を読むのをやめてしまったように、私のような素人が書く文章は、読者の「甘え」に期待できない。素手で立ち向かわなければならない。読んでもらうために、全力で読者を文章へ引きずりこむ必要がある。
ほかにもコツがありそう
机の上で旅行記を書くな
旅行記を見ていると、すべてが過去形で書かれている文が多いことに気がつく。「駅に降りた」のも「話を聞いた」のも「綺麗だと感動した」のも、すべてが過去である。
過去形で書かれると臨場感がまるで感じられない。
「私が駅におりたとき、朝顔の花が色とりどりに咲き誇っていた。今はもう現場にいないので机の上でこれを書いている。」
「私は旅館に着いてはじめて、夏祭りがひらかれていることを知った。今はもう現場にいないので机の上でこれを書いている。」
「私が旅行中は、ちょうどこの地域で夏祭りがおこなわれる季節らしかった。今はもう現場にいないので机の上でこれを書いている。」
───机の上で書いているのかもしれないが、各文章ごとに「机の上で書いています」と告白することはないだろう。旅行記では、大変マイナスに作用すると思う。
紋切型はウソになることがある
紋切型を使うとウソになる場合がある。雪景色といえば「銀世界」。春といえば「ポカポカ」で「水ぬるい」。涙は必ず「ポロポロ」流す。などという、使い古され腐った表現のことをいっている。
「みんな飛び上がって喜んだ」「がっくしと肩を落とした」など、中にはこういう表現をつかった方が文章がうまく見えると考えている人もいるようだが、これは誤解である。
というのも、この種の表現は、気がきいているようで不正確だからである。「銀世界」とは、どの程度に雪が積もっているのだろうか。ある人は1cmくらいと考えるかもしれないし、ある人は1mだと思うかもしれない。
このように、読み手によって解釈が違っては困る。
菫(すみれ)の花を見ると、「可憐だ」と私たちは感ずる。それはそういう感じ方の通念があるからである。しかしほんとうは私は、菫の黒ずんだような紫色の花を見たとき、何か不吉な不安な気持ちをいだくのである。しかし、その一瞬後には、私は常識に負けて、その花を「可憐」なのだ、と思い込んでしまう。文章を書くときに、可憐だと書きたい衝動を感ずる。たいていの人は、この通念化の衝動に負けてしまって、菫というとすぐ可憐なという形容詞をつけてしまう。このときの一瞬間の印象を正確につかまえることが、文章の表現の勝負の決定するところだ、と私は思っている。
野間 宏 編『小説の書き方』(1969年)
紋切型を乱用することは、本質を見のがすことにもつながる。
以上。
参考書籍
外山 滋比古『知的文章術』大和書房(2024年)
本田 勝一『日本語の作文技術』朝日文庫(1982年)